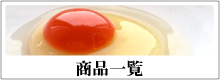| 異業種に学ぶホスピタリティ |
月刊ホテル旅館誌2000年9月号(柴田書店刊)に掲載された経営コンサルタント小林一博先生の『異業種に学ぶホスピタリティ』の記事の全文です。
物価の優等生、タマゴ業界の仕組み
タマゴ(鶏卵)は、今やスーパーの客寄せ目玉商品のエースである。
「特別セール、タマゴ1パック20個10円、お一人様1点限り」などというチラシが家庭に入ると家族総動員でスーパーにかけつけ、1人1パックずつ手に持ちレジに並ぶという光景は、日常茶飯事、もはや当たり前のこととなっている。
このタマゴは、戦後、ほとんど変わらない物価の代表選手として有名だ。物価の変わらいものを挙げよ、と問われれば、誰でもまず、最初にタマゴのことが頭に浮かぶと思う。
昭和30年代も現在も、ほぼ一個10円、40年以上ほとんど価格は変わっていないのだ。
東京の下町で育った私は、昭和30年代の幼いころ、カゴといくらかのお金を持たされて、タマゴを近所の乾物屋にタマゴを買いに行かされた。帰る道々、タマゴを割らないようにこわごわと歩いた記憶が今でも鮮明に残っている。
要するに、昔もいまもどんなに時代が変わっても、タマゴは、一貫して庶民の不朽の人気の食べ物なのである。
連載第二回は、これだけ普及している食べ物でありながら、ほとんど実態が知られていない鶏卵業界と、そのなかで、一部の業者が必至に努力している、その知られざるホスピタリティのありようを取り上げてみたい。
まず、鶏卵(タマゴ)業界の仕組みをご紹介したい。
実は、かなり原始的な仕組みなのである。
この業界の特徴的は点は、飼料業者が問屋を兼ねているということだ。飼料業者は、まず、鶏卵業者に飼料を収める。そして、その対価として飼料業者は、鶏卵業者からタマゴの現物を受け取る。飼料業者はそのタマゴを問屋としての立場で、小売店や二次問屋に納める。
この仕組みを鶏卵業者サイドから見れば、飼料代よりも納めるタマゴが多ければ、その分が儲けとなり、納めるタマゴが少なければ、赤字ということになる。つまり、実質物々交換に近い状態なのである。これが鶏卵業者特有の仕組みなのだ。流通業でいえば、鶏卵業者はメーカーの下請け業者に近い存在であろうか。
鶏卵業界は深刻な過当競争のまっただなか
しかし、いくら原始的といっても、このような状況は、他産業と類似しており、なぜ、タマゴだけが、戦後一貫して、安値で安定しているのだろうか。
その最大の理由は、とにかく各鶏卵業者が、売上増を狙い、どんどんタマゴをつくってきたことにある。一般業種のメーカーであれば、生産量を増やすには、土地を手当てし、設備投資をし、人を増やさなければならないが、鶏卵の場合は、ただ、ニワトリを増やせばそれで済む。土地がなければ、鶏舎を2段3段にすればよい。人件費はニワトリが増えてもあまり大きくは変わりはしないし、上述のように、飼料代はタマゴで納めればいい、要するに生産量を増やしても手間もあまり大きく変わらないのである。相場が下がっても、どんどんつくればそれでいいのだ。
結果として、消費者には、安価なタマゴが届くことになり、消費者もまた、安価で栄養豊富、どんな料理にもマッチするタマゴは重宝であり、どんどん消費する。日本のタマゴをめぐる需給関係はこんな構図になっているのだ。
しかも、バブル期前後から、鶏卵業者が、さらなる売上増を狙い、競って施設を大型化、近代化し、ニワトリを大幅に増やしたため、市場での需給バランスが深刻なまでに完全に崩れてしまった。この結果が「1パック20個10円」なのである。
もはや、業界こぞっての談合による生産調整以外に、打つ手はないだろうというのが、業界の内々の話であると聞く。もちろん鶏卵業者も自衛策として、質の良くない低廉な人工飼料を用いたり、市況の悪いときには冷蔵庫で保管し、市況の良いときに市場に出す、というような工夫(!?)をしているが、実際には資金繰りが極度に悪化して、倒産に近い状態の鶏卵業者も多数出ているのだ。
鶏卵業界はすでに構造的な不況に陥っているという言いかたをしてもよく、業界全体が飼料業界に強い影響力のある大商社の傘下に、組み込まれつつあるのが本当のところだ。
もちろん、大資本参入がすべて悪いということにはならないが、資本の論理が優先し、質の良くないタマゴが日本をおおってしまうのは怖い。
事実、業界の飼料の研究とは、現状の飼料から何を抜いても大丈夫なのか、というコストダウンの研究ばかりだ、と言う業界事情通の話もある。
結果としては、当然、あまり質の良くないタマゴが出回ることになる。わかりやすい言いかたをしれば、水っぽい、おいしくないタマゴが消費者に届くことになるのである。
このような、安かろう悪かろうに傾斜していく業界状況の打破を狙って、最近、各鶏卵業者が競って出しているのが、いわゆるブランドタマゴ(業界用語で特殊卵という)だ。1980年に出た「ヨード卵光」はそのはしりであろうが、現在では、「森林のたまご」「ビタミンBたまご」「北海道赤たまご」「伊豆の新鮮たまご」「信州の自然たまご」といったようなブランドタマゴが関東一円のスーパーや百貨店の鶏卵売場で所狭しと並び、競い合っているが、このような動向はすでに全国に広がっている。
“おいしいタマゴ”とは。『高橋養鶏場』の挑戦
タマゴの市場は全国で約9000軒の業者が、年間248万トンを出荷しているといわれる。
国民一人あたり年間20.7kg、スーパーで売られているMサイズに直すと、年間310~330個ほぼ全国民が毎日1個ずつ食べている計算なのである。
これだけ身近な食べ物でありながら、案外、おいしさや安全性について、おおきな議論がなされていのは実に不思議なことだ。
ここで、埼玉県日高市にある、高橋養鶏場という比較的小規模な鶏卵業者の挑戦を取り上げてみたい。高橋養鶏場は、3代目経営者の高橋尚之氏が経営する鶏卵業者だ。高橋氏もまた施設を大型化、近代化し、大量生産、大量販売を繰り返すなかで、いつの間にか鶏卵業として経営が追い込まれていくさまを見るにつけ、違和感を感じたひとりだった。
タマゴは食品でありながら「おいしさ」の議論がなされていない、業界でもまったく「おいしい」ことに対する理解がないことに気がつき、「おいしいたまご」という当たり前のことに挑戦しようと思い立った。「おいしいたまご」であれば、業界の陥っている悪循環から逃げられるのではないかとも考えたのがその理由だ。
「おいしいたまご」を問屋を通さず直接に消費者に販売すれば、市販のタマゴより高くても消費者の支持は必ずある。結果、問屋主導の価額から離れて、独自の適正価額で販売できるという考えかただった。
挑戦は、70年代中頃より始まり、評判の良い鶏卵業者のタマゴのつくりかたを学び、飼料として漢方薬、一般食品の研究、鶏種、および生育環境の研究などに没頭した。
当然のごとく当時の業界からは異端児扱いされ、父親(先代)からも首を傾げられる毎日だったが、ようやく商品として完成したのが、85年であった。しかし、これは苦闘の始まりにすぎなかった。
自信満々に売り出したタマゴだったが、さっぱり売れないのだ。養鶏場で直接販売したり、近隣の団地に売りに出歩いても、売り上げはまったく上がらなかった。救いは、購入者の評判が良いことだけだった。売れないのは当然だった。割高のわりには、ブランドタマゴほどの知名度、信用度がないこと、高橋養鶏場の立地が、工場団地の外れという販売には適さない、とんでもない、立地だったのだった。
しかし、次々と起こってきたブランドタマゴの興隆が高橋氏には追い風となった。タマゴは皆同じではないということに消費者は気がつき始めたのだ。その後も苦闘は続いてはいたが、年を経るごとに少しずつ売り上げが上がり、7~8年を経て、93年頃にはようやく赤字を出さないまでになった。そして2000年の現在では、知る人ぞ知る「おいしいたまご」として全国から注文が来るまでになったわけである。
実は、高橋氏は、最近次々と販売されるブランドタマゴには懐疑的なのだ。「ヨード入り」という「ビタミン添加」、「カテキン入り」などのような「何かひとつ飼料に加える」ことによって、表面的に、作為的にブランドをつくっても、簡単に品質は上がるわけでもないし、だいたい、おいしいタマゴにはならないと考えているのだ。
高橋養鶏場では、近海いわし、海藻、うこん、食塩、天然ミネラル、木酢液、かきがら、大豆、無農薬・非遺伝子組み替えコーンなど20種以上の飼料を用いている。もちろん使用する飼料はすべて無添加・ノーケミカル(非化学製品)を徹底している。
そして、何よりも特筆すべきは“人間でも食べられる”飼料であることだ。最近ようやく良心的、先進的な鶏卵業者が増えてきてはいるが、人間が食べることのできる飼料を用いている業者はそう多くはないだろう。
高橋養鶏場のタマゴはすごい。割った瞬間に赤黄色も黄身が盛り上がる、目玉焼きの際には、なかなかシンまで火が通らないので普通のタマゴより時間がかかる。つまりこれはタマゴが生きているということの証拠である。
しかし、高橋氏はたんなる見栄えに対しての評価をそれほど歓迎していないようだ。高橋氏の言によれば、テレビのグルメ番組で紹介されるような黄身が盛り上がるタマゴや、“地卵”と称するカラの赤いタマゴなどは、飼料を工夫すれば簡単につくれる、それは品質には直接関係ないと言う。まして「おいしいたまご」とは、そういったわかりやすい見栄えとはほとんど関係ないと言う。
基本コンセプトは、バック・ツー・ベーシック!!
ひと昔前の農家の庭先を思い浮かべれば、適当に放たれたニワトリが勝手しだいに歩き回り、自然の雑草を食(は)み、ミミズをついばみ、春夏秋冬の自然とともにタマゴを生み、ひなを育てる。
どこの田舎でも普通に見られた光景だが、多分、このような環境から生まれたタマゴが、いちばんおいしいタマゴになるのだろうと思う。
“タマゴかけご飯”という単純素朴で、もっともおいしい日本人の家庭食の代表選手は、これで立派に成立するはずだ。
高橋養鶏場のホームページを覗くと、随所に“自然の恵み”という言葉が使われている。
これを見ると、「そうか、タマゴは機械でつくられたものではなく、自然の恵みだったのか」ということを改めて思い起こされてしまうのだ。
しかし、見方を変えれば、高橋養鶏場で行われているタマゴの生産方法、つまり自然の飼料、自然の水、自然を取り入れた飼養環境、そして国産ニワトリも、何のことはない、単に昔のタマゴの生産方法に近づけているだけに過ぎないことになりはしないだろうか。
今、ホテル・旅館業において、しきりにホスピタリティの重要性が語られているが、ここでも必ず、昔の女将の接客や、老舗ホテルの支配人のありかたが話題になる。「バック・ツー・ベーシック」が真剣に語られているのだ。
大量生産、大量販売が招いた質の低廉化は、タマゴの世界だけではなく、ひょっとして旅館・ホテル業においても、あるいは、日本中のすべてのビジネス社会においても行われていることではないのかとも考えさせられてしまうのだ。同質の問題が日本全体をおおっているのかもしれない。
もちろん、高橋養鶏場で行われていることはホスピタリティとはまったく無縁の実験だ。
しかし、高橋氏なりに顧客の健康を考え、良心的な商品のありかたを追求したそのプロセスのどこかに、顧客を大切にするというホスピタリティを感じてしまうのは私だけではないだろう。
高橋養鶏場のありかたを見ていると、何も難しい話ではなく、不自然なことをやらずに顧客を大事にする、商品を大事にするという当たり前の努力がホスピタリティの原点ではないのだろうか、ということを改めて考えさせられてしまうのだ。
そして、いつか必ず、顧客はその努力に気がつくのだ。
*******************************************************************
|
|
筆者: | 小林一博(こばやし・かずひろ) |
|
|
|
1950年生まれ、日本大学法学部卒業。 赤札堂、東天紅などの小泉グループに入社。84年モスフードサービスに社。広報室長。上場プロジェクトを担当。90年船井総研の関連会社設立に参画。 同社の取締役を経て、95年(有)小林企業成長研究所を設立。 現在、同社の代表取締役を務める。 |